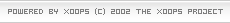-
遅くなりましたが,明けましておめでとうございます。これを読んでいるみなさんにとって,実り多き年となりますように願っています。年明けからいろいろと,個人的なプロセスの大きな展開があって,その流れが一段落した感じで書いてますけど,何か今年は大きく発展したり変わっていきそうな感じがしています。クリエイティヴ・セラピー(創作コラージュ療法)の方も,今年は全体的に大きな動きがあるので,忙しくなりそうですが,できるだけ更新も遅れないようにしていきたいので,今年もよろしくお願いします。プライベートなことなので詳しくは書けませんが,あきらめかけていた長年の願いが叶ったと思えることがありました。みなさんも,自分の願いをあきらめないでほしいと思っています。それでは,1年の初めなのでまた抱負という感じで書いていきますね。
初夢というものが1年を占うということは伝統的に言われていますが,臨床におけるイニシャル・ケースとかイニシャル・ドリームのように,大きな方向づけを象徴的に示しているものだと思います。なので,1年の初頭にある場所とか領域で起こってくることは,恐らくその場所や領域でのその後の展開というものを暗示しているのではないかと。その意味では,今年は初頭から何度も,臨床について今まで自分が考え続けてまとまってきたことを信念をもって伝えていく,ということが繰り返されているので,これまでも学会発表を通してある程度はやってきたけれど,たぶんもっと自分の個性を出して主張していったりすることになるかなと思います。今までは遠慮していた部分もあったけれど,今年の初めにある出会いがあって,自分の考えていたことが間違っていなかったと自信を深めることもあったので,カウンセリング/心理療法の本質的な部分を伝えていけるように,努力を傾けていきたいと思っています。
初夢というものが1年を占うということは伝統的に言われていますが,臨床におけるイニシャル・ケースとかイニシャル・ドリームのように,大きな方向づけを象徴的に示しているものだと思います。なので,1年の初頭にある場所とか領域で起こってくることは,恐らくその場所や領域でのその後の展開というものを暗示しているのではないかと。その意味では,今年は初頭から何度も,臨床について今まで自分が考え続けてまとまってきたことを信念をもって伝えていく,ということが繰り返されているので,これまでも学会発表を通してある程度はやってきたけれど,たぶんもっと自分の個性を出して主張していったりすることになるかなと思います。今までは遠慮していた部分もあったけれど,今年の初めにある出会いがあって,自分の考えていたことが間違っていなかったと自信を深めることもあったので,カウンセリング/心理療法の本質的な部分を伝えていけるように,努力を傾けていきたいと思っています。
あっという間に年末に入りましたね〜。まだ年末の実感なんてないんだけど,1年を振り返るといろいろあったなあという感じ。臨床とは関係ないけど,熱帯夜の真っ最中に寝室のエアコンが壊れて寝不足だったとか,冷え込みが厳しくなった時には給湯器が壊れて銭湯通いをしたら本格的に風邪をひいたとか,まあ何かと古いものが壊れるという感じ。賃貸で築年数も結構なものだし,しょうがないんだけど。でも,新しくなると以前より快適になるから,結果的には良かったし,そういう,古いものが新しく変わるという流れにあったのかもね。臨床的には,いろいろ見えてきたこともあったり,まあそれはおいおい書くとして,初めての関東以外の学会発表というのが目新しかったかな。来年は九州だと。遠いけど,今のところまた発表予定です。もう大会関連の第一弾書類発送が来てるし。今まで発表したものも,論文にまとめ始めないとなので,何かと来年は忙しい。新しい講座の企画もあるしね。
ということで今回は,「認定クリエイティヴ・セラピスト養成講座」に水曜講座が新設されるので,それについて書きます。2011年3月で,僕がクリエイティヴ・セラピーに出会って10周年となるので,その節目ということもあって,2011年度からは講座関連を大きくリニューアルすることにしました。水曜講座の新設はもともと,主婦の方など土日より平日の方が受講しやすいという方から要望があって検討していたものですが,実現できる見通しがついたのでこれを機に開講となります。講座の内容自体もリニューアルしますが,主に臨床心理学講座の方で,カリキュラムを整備して基本的な流れに沿って学習が進められるようにします。もちろん,今までも配慮してはいましたが,ロールプレイも含めてより体系的に進められるようにと思っています。また,臨床心理学講座は,半年ごとに臨床心理学の部と深層心理学の部という形で整備して,体系的な学習ができるようになります。
ということで今回は,「認定クリエイティヴ・セラピスト養成講座」に水曜講座が新設されるので,それについて書きます。2011年3月で,僕がクリエイティヴ・セラピーに出会って10周年となるので,その節目ということもあって,2011年度からは講座関連を大きくリニューアルすることにしました。水曜講座の新設はもともと,主婦の方など土日より平日の方が受講しやすいという方から要望があって検討していたものですが,実現できる見通しがついたのでこれを機に開講となります。講座の内容自体もリニューアルしますが,主に臨床心理学講座の方で,カリキュラムを整備して基本的な流れに沿って学習が進められるようにします。もちろん,今までも配慮してはいましたが,ロールプレイも含めてより体系的に進められるようにと思っています。また,臨床心理学講座は,半年ごとに臨床心理学の部と深層心理学の部という形で整備して,体系的な学習ができるようになります。
また更新が遅れてごめんなさい。最近,多忙が重なって疲れがなかなか抜けないので,文章を書くのがちょっと大変な感じでした。ここ数日,心身を休められたので,ようやく書ける感じになってきたかなというところ。と言いつつも,まだ風邪気味なんだけど,まあ少し頑張って書きますね。今回は,心身の症状と薬物療法について,考えていることを書いてみようと思ってます。
セラピスト自身の心身をケアすることが大事なのは,改めて言うまでもないことだけど,まず最低限クライエントさんの面接に穴を開けないということ,そしてセラピスト自身の問題を面接の場に持ち込まないこと。前者は主に体調管理ということになるし,後者は主に心理的なコンディションをコントロールできることが関係していることになる。でも,事はそれほど単純ではなくて,クライエント−セラピスト間で起こっている関係性が,セラピストの心身の状態に影響を与えているということもあるので,いわゆる世間的な自己管理とかコントロールということを重視しすぎると,方向がずれることがある。一般的な自己管理などのニュアンスは,起こっている心身の状態を抑圧的にコントロールすることに重点が置かれるように思うけど,クライエント−セラピスト間で起こっている関係性がセラピストに影響している場合に,その何らかの不調が抑圧されるのは好ましくない。セラピストは少なくとも,その心身の不調に対して気づき,抑圧的にならずにその不調と共にあるという姿勢を持っていることが,関係性やカウンセリング/心理療法の方向性に気づきをもたらしてくれる。
セラピスト自身の心身をケアすることが大事なのは,改めて言うまでもないことだけど,まず最低限クライエントさんの面接に穴を開けないということ,そしてセラピスト自身の問題を面接の場に持ち込まないこと。前者は主に体調管理ということになるし,後者は主に心理的なコンディションをコントロールできることが関係していることになる。でも,事はそれほど単純ではなくて,クライエント−セラピスト間で起こっている関係性が,セラピストの心身の状態に影響を与えているということもあるので,いわゆる世間的な自己管理とかコントロールということを重視しすぎると,方向がずれることがある。一般的な自己管理などのニュアンスは,起こっている心身の状態を抑圧的にコントロールすることに重点が置かれるように思うけど,クライエント−セラピスト間で起こっている関係性がセラピストに影響している場合に,その何らかの不調が抑圧されるのは好ましくない。セラピストは少なくとも,その心身の不調に対して気づき,抑圧的にならずにその不調と共にあるという姿勢を持っていることが,関係性やカウンセリング/心理療法の方向性に気づきをもたらしてくれる。
カレンダー的には3連休だった週末,急性腸炎になってしまい,38度台の熱と腹痛で大変でした。具合が悪いと思いながら,カウンセリング/心理療法の予約に穴は開けられないので,金曜に無理をして仕事をしたら,土曜日にしっかり悪化してくれた。ノロウィルスとかインフルエンザとか,感染性の強いものはクライエントさんにうつすといけないので事情を話して休みますけどね。ちょっとやそっと具合が悪くても,セラピストのキャンセルというのは関係性を中心にいろいろ影響があるので,そう簡単には休めません。ただ,意識がもうろうとして面接に支障をきたすようなら,やむを得ないかなと思うけど。まあ,平熱が低い僕にとっては,38度って充分もうろうなんだけど,なぜか面接の時は大丈夫だったりする。
さて,9月の下旬に,クリエイティヴ・セラピー関連の合宿研修があった。何度か書いているけど,クリエイティヴ・セラピー(創作療法)は創作コラージュ療法が中心になることが多い。それは,心理検査としての高度なアセスメント技法でもありながら,心理療法としての活用でも積極的なフィードバックによる有効な成果をあげているという,カウンセリング/心理療法の両輪といってもいいアセスメント+サイコセラピーの両面を備えているからだ。でも,今回は創作コラージュ療法についてはあまり触れず,ドイツ語文化圏では中心的な心理検査として使われておりバウムテストを超える評価を得ているといわれる,ワルテッグ・ツァイヒェン(一般には「ワルテッグ描画テスト」として知られる)の分析技術の向上を中心的な目的としていた。ワルテッグ・ツァイヒェンは空間象徴理論を背景として8つの描画枠の組合せで,心理状態やパーソナリティ傾向を読み取っていく。この空間象徴理論の応用は非常に巧みに構成されているので,このアセスメント技術の向上は,同様の空間象徴理論を活用している創作コラージュ療法の分析技術の向上につながるということになる。
さて,9月の下旬に,クリエイティヴ・セラピー関連の合宿研修があった。何度か書いているけど,クリエイティヴ・セラピー(創作療法)は創作コラージュ療法が中心になることが多い。それは,心理検査としての高度なアセスメント技法でもありながら,心理療法としての活用でも積極的なフィードバックによる有効な成果をあげているという,カウンセリング/心理療法の両輪といってもいいアセスメント+サイコセラピーの両面を備えているからだ。でも,今回は創作コラージュ療法についてはあまり触れず,ドイツ語文化圏では中心的な心理検査として使われておりバウムテストを超える評価を得ているといわれる,ワルテッグ・ツァイヒェン(一般には「ワルテッグ描画テスト」として知られる)の分析技術の向上を中心的な目的としていた。ワルテッグ・ツァイヒェンは空間象徴理論を背景として8つの描画枠の組合せで,心理状態やパーソナリティ傾向を読み取っていく。この空間象徴理論の応用は非常に巧みに構成されているので,このアセスメント技術の向上は,同様の空間象徴理論を活用している創作コラージュ療法の分析技術の向上につながるということになる。
毎度のことながら,更新が遅れてごめんなさい。学会発表が終わって,しばらく気が抜けたというか,ギリギリまで準備をしていたのでやりきった感があって,逆に振り返る時間が必要だったかなと思います。やりきったといっても,まあ反省点は残っているけど,今回はあまり緊張しないでやれたので,古武術の練習での心の持ち方が活かせるようになってきたかなという感じ。反省点ははまた次回に活かしていこうということで,今のところ来年も発表しようとは思っています。来てくださった方,改めてありがとうございました。よかったらまた,来年お会いしましょう。
今回の発表で,事例を通した考察では,プレイセラピーに加えて他機関で療育が実施されるようになった影響で,クライエントが身につけた適応行動がロボット化してしまったことを通して,プレイセラピーにせよ療育にせよ,それを行う援助者の心理的な姿勢,あり方(being)が大きく影響を与えていくということを伝えようとしました。ひいては,クライエントさんとの関係性に関わってくる重要な点で,ある意味当然とも言えることではあるけれど,何か技法を用いようとかするときに,ついついずれていきがちなところでもあると考えてます。つまりは,クライエントさんに心を向けた関係性ではなくなって,技法に心が向いてしまってセラピストと技法との関係が主になってしまうということがあり得るわけです。基本中の基本ともいえることだけれど,絶えず気をつけていないとずれていってしまうと考えていて,それを伝えようと思った発表でした。その中で,ウィニコットのholdingなどに言及したんだけど,フロアから僕が「どのようにholdingしているのか」という質問があったので,補足を兼ねて書きたいと思います。
今回の発表で,事例を通した考察では,プレイセラピーに加えて他機関で療育が実施されるようになった影響で,クライエントが身につけた適応行動がロボット化してしまったことを通して,プレイセラピーにせよ療育にせよ,それを行う援助者の心理的な姿勢,あり方(being)が大きく影響を与えていくということを伝えようとしました。ひいては,クライエントさんとの関係性に関わってくる重要な点で,ある意味当然とも言えることではあるけれど,何か技法を用いようとかするときに,ついついずれていきがちなところでもあると考えてます。つまりは,クライエントさんに心を向けた関係性ではなくなって,技法に心が向いてしまってセラピストと技法との関係が主になってしまうということがあり得るわけです。基本中の基本ともいえることだけれど,絶えず気をつけていないとずれていってしまうと考えていて,それを伝えようと思った発表でした。その中で,ウィニコットのholdingなどに言及したんだけど,フロアから僕が「どのようにholdingしているのか」という質問があったので,補足を兼ねて書きたいと思います。
夏休みは大きなイベントがあって,その疲労回復とでほとんどつぶれました。その分,リフレッシュはできて,学会発表の準備がようやく始まったという感じ。いろいろと考えを巡らせているところです。事例研究なので,事例を通して発表するわけだけど,それをどういう方向でまとめるかは,大まかには見えていても実際にまとめていく過程で変化が出てくる。自分と事例研究の間にある関係性のあり方は,ある種の自律性をもっているような気がする。どういう形で帰結するか,楽しみでもあり,産みの苦しみでもある。その結果は,できれば実際の発表でご覧ください。というわけで,学会発表に向けてプレイセラピーのことを考える一環で,このブログでも書いてみたいと思います。
プレイセラピーの枠ということを考える中に,「限界設定」ということがある。これは,プレイセラピーに限られた考え方ではなくて,境界例の治療論でもよく出てくる。簡単に説明すると,クライエントさんの行動などに何らかの制限を設定することで,ここまではいいけどこれ以上はダメというような,線引きをすること。臨床的には,面接構造上の自我の枠(=守り)をきちんと設定することで,水準的には自我の守りが弱いクライエントさんを守り,その枠の中で安全にカウンセリング/心理療法を展開していくために必要になってくる。プレイセラピーの限界設定としては,遊びの展開があまりにも破壊的だったりする場合に,セラピスト側が限界を設定することで,子ども自身もセラピストも守ることができる。ただ,どこに限界設定の線引きをするかというのは,セラピスト自身の器というか限界もあって,そこを認識していないとセラピスト自身も脅威にさらされるし,かといってあまりにも限界設定が窮屈になると,プレイセラピーとしての広がりや深まりというものも制限してしまう。本質的には,子どもの状態を的確にアセスメントしつつ,子どもが展開するプレイが崩壊に向かわないギリギリのところで設定するのがベストだと思う。
プレイセラピーの枠ということを考える中に,「限界設定」ということがある。これは,プレイセラピーに限られた考え方ではなくて,境界例の治療論でもよく出てくる。簡単に説明すると,クライエントさんの行動などに何らかの制限を設定することで,ここまではいいけどこれ以上はダメというような,線引きをすること。臨床的には,面接構造上の自我の枠(=守り)をきちんと設定することで,水準的には自我の守りが弱いクライエントさんを守り,その枠の中で安全にカウンセリング/心理療法を展開していくために必要になってくる。プレイセラピーの限界設定としては,遊びの展開があまりにも破壊的だったりする場合に,セラピスト側が限界を設定することで,子ども自身もセラピストも守ることができる。ただ,どこに限界設定の線引きをするかというのは,セラピスト自身の器というか限界もあって,そこを認識していないとセラピスト自身も脅威にさらされるし,かといってあまりにも限界設定が窮屈になると,プレイセラピーとしての広がりや深まりというものも制限してしまう。本質的には,子どもの状態を的確にアセスメントしつつ,子どもが展開するプレイが崩壊に向かわないギリギリのところで設定するのがベストだと思う。
今年の心理臨床学会の年次大会は東北大学で,久しぶりに関東から離れる感じ。4回目となる学会発表が決まって,初めて関東から離れての発表で,期待と不安が入り交じったような感じ。仙台は初めてだし,緊張する感じもあったり,放送大学時代の恩師に会える予定なので楽しみでもあったり,なんか複雑な感じ。テーマは,3年連続になる,アスペルガー障害(傾向)のプレイセラピーで,今回は関係性とかセラピスト自身の心理的姿勢といったことが中心になる予定。9月3日の10時30分と,金曜日の一番最初の発表なので,参加者がまだ出てこられない時間になり得るから,少なめになりそう。学会員の方はぜひ見に来てください〜
プレイセラピーは,遊びを通しての関わりになるので,端から見ると遊んでいるだけのように見える。教育相談などで,保護者が子どもから様子を聞いたりして遊んでるだけだと知って,最初は怪訝な表情をされる人もいる。でも,プレイセラピーの意味を説明したり,その機会がなくても,何度か通っているうちにそれまでとは違う形で子どもが変わっていくのがわかってくる。そうすると,保護者も何も言わなくなるし,具体的にはわからなくても,子どもが生き生きとしてくれば何か意味があるのだと感じて,積極的に連れてくるようになる。まあ,中には勉強やトレーニングをさせるという考えが強い保護者もいて,なかなか噛み合わなかったりということもあるし,全部が全部こんなふうに流れるわけじゃないけどね。子どもは遊びという世界の中で育っていくので,勉強やトレーニングを遊びより優先させると,たとえ大人にとって扱いやすい子どもになったとしても,どこかでその歪みが出てくることが多い。
プレイセラピーは,遊びを通しての関わりになるので,端から見ると遊んでいるだけのように見える。教育相談などで,保護者が子どもから様子を聞いたりして遊んでるだけだと知って,最初は怪訝な表情をされる人もいる。でも,プレイセラピーの意味を説明したり,その機会がなくても,何度か通っているうちにそれまでとは違う形で子どもが変わっていくのがわかってくる。そうすると,保護者も何も言わなくなるし,具体的にはわからなくても,子どもが生き生きとしてくれば何か意味があるのだと感じて,積極的に連れてくるようになる。まあ,中には勉強やトレーニングをさせるという考えが強い保護者もいて,なかなか噛み合わなかったりということもあるし,全部が全部こんなふうに流れるわけじゃないけどね。子どもは遊びという世界の中で育っていくので,勉強やトレーニングを遊びより優先させると,たとえ大人にとって扱いやすい子どもになったとしても,どこかでその歪みが出てくることが多い。
また更新が遅くなってごめんなさい。ちょっと最近疲労が強いので,なかなか文章を書くのも大変になっています。最近は,1年半ぐらいやってきた古武術の習得の中で自分の身体の状態や動きがわかるようになってきて,姿勢とか動き方を修正していっているので,そういう影響もあるかも。まだ古い姿勢や動き方の癖が残っているので無理があったり,新しいやり方が入ってくると使わない部分を使ったりするので慣れるまでは疲れるかなという気はしてる。そんなわけで,今回は心理臨床と姿勢や動作に関する話。
心と身体というのは密接に関連していて,比較的無意識レベルの心の奥にあるものが,身体に表現されているということは,ちゃんと調べることができればかなりの相関をもっているはずだ。よく言われる例では,気が滅入ったり落ち込んでると,頭が下を向いて胸が引っ込み背中を丸めるような姿勢になる。逆に自信過剰で我が強すぎると,頭が上を向いて胸が張り出し背中が引っ込むような姿勢になる。漫画の描写を見ると,こういう特徴をもう少し極端にデフォルメしているのでわかりやすいけど,これは人を観察することを通して,表情に加えて姿勢で心理状態をより描写できるようにという作者の工夫に他ならないはず。もう少し専門的には,身体心理学と言われるようなジャンルで扱われている。まあ身体心理学といっても幅広いけれど,身体というものを通して心理的なアプローチを行うという点では一致していると言っていいかなと思う。
心と身体というのは密接に関連していて,比較的無意識レベルの心の奥にあるものが,身体に表現されているということは,ちゃんと調べることができればかなりの相関をもっているはずだ。よく言われる例では,気が滅入ったり落ち込んでると,頭が下を向いて胸が引っ込み背中を丸めるような姿勢になる。逆に自信過剰で我が強すぎると,頭が上を向いて胸が張り出し背中が引っ込むような姿勢になる。漫画の描写を見ると,こういう特徴をもう少し極端にデフォルメしているのでわかりやすいけど,これは人を観察することを通して,表情に加えて姿勢で心理状態をより描写できるようにという作者の工夫に他ならないはず。もう少し専門的には,身体心理学と言われるようなジャンルで扱われている。まあ身体心理学といっても幅広いけれど,身体というものを通して心理的なアプローチを行うという点では一致していると言っていいかなと思う。
昨日,無料体験・公開講座「クリエイティヴ・セラピー」が終わりました。今年もたくさんの方にご参加いただき,アンケートも好感触でした。参加者にみなさんには,改めてこの場でも御礼申し上げます。ブログの方は,何かと忙しくて大幅に更新が遅れてしまいました。楽しみに読んでくださっている方,ごめんなさい。今回は,終わったばかりで,2週間後からまた連続講座が始まる「創作コラージュ療法」についてです。
「創作コラージュ療法」は,芸術療法(アートセラピー)と呼ばれる大きなカテゴリーに入りますが,一般的な芸術療法が「解釈しないことを原則とする」のに対して,「創作コラージュ療法」では,「積極的に投影分析的理解法を用いる」点で大きく異なります。「投影分析的理解法」とは,専門家が解釈を伝えるという一方向ではなく,投影分析の専門的知見を作者と共有してコラージュ作品に表れた気分状態・心理状態を一緒に理解していくという双方向のやりとりである点で,「解釈」と区別しています。これらの点により,カウンセリング/心理療法としての効果も,表現行為によるカタルシスだけでなく,作者(クライエント)自身の自己理解が深まることやそれを共有してもらえる感覚によって何倍にも高められると言えます。これらのことは,これまでも何度か説明してきましたが,後半は芸術療法(アートセラピー)という観点から書いてみます。
「創作コラージュ療法」は,芸術療法(アートセラピー)と呼ばれる大きなカテゴリーに入りますが,一般的な芸術療法が「解釈しないことを原則とする」のに対して,「創作コラージュ療法」では,「積極的に投影分析的理解法を用いる」点で大きく異なります。「投影分析的理解法」とは,専門家が解釈を伝えるという一方向ではなく,投影分析の専門的知見を作者と共有してコラージュ作品に表れた気分状態・心理状態を一緒に理解していくという双方向のやりとりである点で,「解釈」と区別しています。これらの点により,カウンセリング/心理療法としての効果も,表現行為によるカタルシスだけでなく,作者(クライエント)自身の自己理解が深まることやそれを共有してもらえる感覚によって何倍にも高められると言えます。これらのことは,これまでも何度か説明してきましたが,後半は芸術療法(アートセラピー)という観点から書いてみます。
3月の怒濤の忙しさと新年度の慌ただしさが一段落した感じだけど,また新しいことを勉強し始めたりもしているので,忙しさはあまり変わらないかも。空くと何か入れたくなる強迫的な性分なんだけど,まあ忙しくて中断してた機器の改造なんかも,再開し始めたので,気持ちにゆとりが出てはきているかなと。今日はゆとりなどのカウンセラー/セラピストの姿勢に関する話です。
カウンセラー/セラピストとしては,カウンセリング/心理療法を行う時には気持ちにある程度のゆとりがあった方がいい。緊張感はある程度必要だけど,余裕がない状態は視野を狭めるので,微妙な部分に気がつくアンテナの感度が悪くなる。フロイトの言う「平等に漂う注意」ができるようになるにはこの余裕とかゆとりが必要で,その漂う注意の中で浮かび上がってくる何かをつかみとることができると,面接が深まっていく。プロセス指向心理学(プロセスワーク)の創始者のパートナーであるエイミー・ミンデルは,これを魚釣りにたとえていたりする。魚釣りでは,茫漠として拡散した注意力で魚がかかるのを待ち,魚がかかると釣り竿と魚の反応に集中する。カウンセリング/心理療法でも,この拡散した注意力を発揮できるかどうかは,1回の心理面接の中でもその展開に大きな影響を与える。ミンデルの言うところは,「平等に漂う注意」よりもさらに微妙で繊細なもの・・「雰囲気」とでも形容したらいいかな・・をつかみとることを指しているので同義ではないけれど,セラピストの姿勢という点ではかなり類似していると思う。
カウンセラー/セラピストとしては,カウンセリング/心理療法を行う時には気持ちにある程度のゆとりがあった方がいい。緊張感はある程度必要だけど,余裕がない状態は視野を狭めるので,微妙な部分に気がつくアンテナの感度が悪くなる。フロイトの言う「平等に漂う注意」ができるようになるにはこの余裕とかゆとりが必要で,その漂う注意の中で浮かび上がってくる何かをつかみとることができると,面接が深まっていく。プロセス指向心理学(プロセスワーク)の創始者のパートナーであるエイミー・ミンデルは,これを魚釣りにたとえていたりする。魚釣りでは,茫漠として拡散した注意力で魚がかかるのを待ち,魚がかかると釣り竿と魚の反応に集中する。カウンセリング/心理療法でも,この拡散した注意力を発揮できるかどうかは,1回の心理面接の中でもその展開に大きな影響を与える。ミンデルの言うところは,「平等に漂う注意」よりもさらに微妙で繊細なもの・・「雰囲気」とでも形容したらいいかな・・をつかみとることを指しているので同義ではないけれど,セラピストの姿勢という点ではかなり類似していると思う。